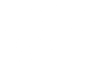自己紹介
更新情報
以下の講演,学会発表が予定されています。
数智时代下基于决策树分析的语言研究
日時:2025年5月29日(木)
場所:天津外国语大学马场道校区逸夫楼大江厅
講師:玉岡賀津雄(上海大学、名古屋大学)
要約:玉岡教授の著書『基于决策树分析的语言研究』(黒潮出版社)は、2023年7月10日に正式に出版されました。本書では、「決定木分析」が言語研究にどのように応用できるかを体系的に紹介しており、主に分類木分析と回帰木分析の2つの手法を取り上げています。分類木分析は、コーパス頻度のような非パラメトリック・データ(質的変数)の予測に適しており、一方の回帰木分析は、テスト得点などのパラメトリック・データ(量的変数)の予測に適用されます。本講演では、「数智時代(デジタル・インテリジェンス時代)」を背景として、2つの具体的な研究事例を通じて、分類木分析と回帰木分析を言語学研究に効果的に活用する方法を、段階的にわかりやすく解説いたします。内容は平易で、さまざまな参加者にとって理解しやすいものとなっております。1つ目の研究は回帰木分析を用いたもので、疑問形式や否定表現を含む文が、より丁寧な表現として受け取られるかどうかを検証します。この研究では容認性判断課題を通じて、人間の丁寧さに関する本質的な認知メカニズムを明らかにします。2つ目の研究は分類木分析を用いて、中国人日本語学習者が助言をどのように表現するかを、ポライトネス理論の観点から分析します。この研究では、日本語学習を通じて生じる文化的適応現象や、中国語母語話者の文化的慣習が日本語使用に及ぼす「逆行転移」の影響についても検討します。本講演では、実用的な分析手法の紹介だけでなく、言語・文化・認知がどのように絡み合うかという複雑な関係性も取り上げます。言語研究、異文化コミュニケーション、あるいはデータ分析手法に関心をお持ちの学生・研究者の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
オノマトペは語彙か?感覚か?―外国人日本語学習者によるオノマトペ習得―
日時:2025年6月XX日(X)
場所:上海財経大学(国定路777号)
講師:玉岡賀津雄(上海大学、名古屋大学)
要旨:日本語のオノマトペ(擬音語・擬態語・擬情語)は、音と意味の結びつきが強い「音象徴語」として知られ、幼児期の日本語母語話者においては自然なコミュニケーションの中で早期に獲得される語彙群である。縦断的・横断的研究により、日本語母語児は擬態語よりも擬音語を先に習得する傾向があることが報告されている(大久保, 1967; 福田・芋阪, 1999)。こうした音象徴語の有契性は、特定の言語環境の中で自然に形成されたものであり、音と意味の恣意的な結びつきを伴うものである可能性がある。一方、外国人日本語学習者にとって、オノマトペは母語環境に根ざした感覚的語彙というよりも、教室で習う“語彙アイテム”として捉えられる傾向がある。本講演では、日本語を外国語として学ぶ学習者が、オノマトペをどのように理解し、習得しているかを検討し、母語話者とは異なる「語彙的習得」の実態を明らかにする。
日時:2025年8月23日から24日
場所:西安、西安電子科技大学
講師:玉岡賀津雄(上海大学、名古屋大学)
要旨: 中国語や日本語では、「面子(フェイス)」という語が日常的に使われており、「面子を立てる」「面子を潰す」「面子を保つ」といった表現に見られるように、対人関係において重要な意味を持つ。英語にも save face という表現があるように、フェイス概念は多文化に共通する対人行動の基盤である。Brown & Levinson(1978, 1987)のポライトネス理論は、このフェイス概念に基づき、発話行為が相手のフェイスをどの程度脅かすか(Wx)を、話し手と聞き手の社会的距離(D)、聞き手の力(P)、行為自体の負担度(Rx)から算出する公式(Wx = D + P + Rx)で表した。この理論は、Wxが低ければ率直な発話が可能であり、Wxが高い場合は発話を避ける、あるいは極めて婉曲な表現をとるという前提に立っており、滝浦(2005)による紹介以降、日本語教育や対人コミュニケーション研究に広く影響を与えてきた。
しかし、この理論におけるRxは、社会的距離(D)や権力関係(P)では捉えきれない「その他すべての要因」を含んでおり、心理的・文化的要素を一括して扱う「ゴミ箱(garbage can)」のような位置づけとなっている点に課題がある。こうした曖昧性に着目したのが、Banerjee & Carrell(1988)である。彼らは助言場面における「相手を恥ずかしがらせる程度(degree of embarrassment)」という心理的要因に注目し、フェイス侵害の程度を(1)恥ずかしさがない、(2)軽い恥ずかしさ、(3)強い恥ずかしさの三段階に分類し、発話選択との関係を精緻に分析した。実際、私たちは日常会話において、助言すべきかどうかに迷うことが多い。助言行動は、単に社会的距離や上下関係といった社会的要因だけでなく、「相手がどう感じるか」「どこまで踏み込んでよいのか」といった心理的配慮にも左右される。また、中国人日本語学習者にとっては、母語であれば助言をためらわない場面でも、日本語という外国語を用いることで判断が揺らぐことがある。そこには、「文化適応(cultural adaptation)」や学習した外国語の持つ価値観からの「逆行転移(retroactive transfer)」といった要因も関わっていると考えられる。
本講演では、日本人および中国人の母語における助言行動の特徴を比較した上で、中国人日本語学習者が日本語と中国語でどのように助言を行うかに注目し、社会的要因、心理的要因、日本語学習による文化適応、そして中国文化への逆行転移といった複合的要因の影響を分析する。とくに助言の難しさを決定づける要因を、回帰木分析(決定木分析の一種)によって可視化し、理論的背景としてのポライトネス理論が持つ「社会的要因への偏り」と「Rxの曖昧性」を再検討することで、より多層的で実践的なポライトネス理解の可能性を提案したい。
![]()
TEL 090-7774-3124
E-mail:tamaoka@nagoya-u.jp ktamaoka@gc4.so-net.ne.jp